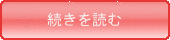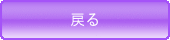千里山移転が関西大学発展の礎に 関西大学の前身、関西法律学校は明治19年(1886年)11月4日、大阪市西区京町堀上通3丁目36番地の願宗寺で創立されました。ボアソナード博士のフランス法律を学んだ門弟、裁判官たちが児島惟謙控訴院長。 のもとに集まり、庶民のために開かれた学校でした。この学校が大正7年(1918年)に公布された文部省による大学令で、正式な大学昇格のためには相当広大な校地と校舎が必要となり、新しい校地として白羽の矢を立てたのが郊外の千里山でした。大正10年(1921年)7月、千里山学舎の建設が着工され、翌11年(1922年)4月に2階建て、延1226坪の学舎が竣工しました。同年6月大学令による大学として、関西大学の認可が文部省より下され、昇格を果たすことができました。いわば千里山への移転で、今日の関西大学の原形が整備されたのです。そして、その後の同大の発展の礎となったのです。
のもとに集まり、庶民のために開かれた学校でした。この学校が大正7年(1918年)に公布された文部省による大学令で、正式な大学昇格のためには相当広大な校地と校舎が必要となり、新しい校地として白羽の矢を立てたのが郊外の千里山でした。大正10年(1921年)7月、千里山学舎の建設が着工され、翌11年(1922年)4月に2階建て、延1226坪の学舎が竣工しました。同年6月大学令による大学として、関西大学の認可が文部省より下され、昇格を果たすことができました。いわば千里山への移転で、今日の関西大学の原形が整備されたのです。そして、その後の同大の発展の礎となったのです。
千里山と関西大学とは深い結び付き 千里山丘陵地への関西大学の移転は、大阪住宅会社の住宅開発とともに、丘陵地の開発を成し遂げ、吹田市域に多くの大学を誘致する端緒となったのです。関西大学と千里山との結び付きは、千里山住宅地開発。 の発起人で、そのために設立された大阪住宅経営㈱の社長を務めた当時の大阪商工会議所会頭の山岡順太郎氏が、後に関西大学学長に就いているように地域的にはもちろん、人脈的にも極めて深いものがあります。山岡氏は大阪住宅経営㈱で、この事業は社会的事業であるとし、俸給は一切受け取らず責任を果たし、社会と会社のため尽くされたといいます。
の発起人で、そのために設立された大阪住宅経営㈱の社長を務めた当時の大阪商工会議所会頭の山岡順太郎氏が、後に関西大学学長に就いているように地域的にはもちろん、人脈的にも極めて深いものがあります。山岡氏は大阪住宅経営㈱で、この事業は社会的事業であるとし、俸給は一切受け取らず責任を果たし、社会と会社のため尽くされたといいます。
人気集めた千里山遊園は廃業、現在、関西大学施設に 千里山遊園は大正10年(1921年)、大阪電気鉄道が千里山花壇として開園し、昭和13年(1938年)、千里山遊園と改称されました。園内には飛行塔、野外音楽堂、ボート池、人工滝、小動物園などの施設があり、人気を集めていました。昭和21年(1946年)には菊人形展が開催されました。しかし戦後、枚方パークで菊人形展が再開されたため、千里山遊園は衰退し、昭和25年(1950年)に廃業しました。閉園後、関西大学が跡地6万6120㎡を購入し、関西大学外苑と命名しました。その後、関西第一中学校・高等学校が設置され、野外音楽堂だったところも創立百周年記念会館が建てられています。
千里ニュータウンは全国の建設計画のモデルに 千里ニュータウンは高度経済成長期、都市への人口集中による住宅不足、土地の乱開発による住環境悪化に対応するために大阪府企業局が開発した日本で最初の本格的な計画人工都市です。昭和33年(1958年)5月、開発決定がなされ、昭和35年(1960年)10月にはマスタープランがまとめられました。単なる団地ではなく、健康で文化的な生活を享受でき、様々な交通網やアメニティ施設を整えた「理想的な住宅都市」を目指し、基本的なコンセプトは「大阪近辺に勤務する中低所得者を主体に、一部高額所得層を加えた安定した住宅地域で、独自の文化をもつまち」でした。千里ニュータウンの計画は、後に作られる全国のニュータウン建設計画のモデルプランとなり、大きな影響を与えました。
昭和36年(1961年)7月、起工式が行われ、昭和37年(1962年)9月には佐竹台で第一期入居が開始され、11月に街開きが行われました。それまで地縁、血縁を持たない人たちが集まった住民たちは新たにコミュニティーを形成し、文化施設を作り、イベントを実施して新たなふるさとにしていきました。
人口減少と高齢化、老朽化で再整備が課題に 千里ニュータウンの目標人口は3万戸(その後3万7000戸)15万人でしたが、人口は昭和50年(1975年)の約12万9000人をピークに、次第に減少傾向をたどっています。そのため、市は対策に乗り出し、平成22年(2010年)現在、少子核家族化による人口減少と高齢化問題、住宅の老朽化、近隣センター、地区センターの活性化、良好な自然環境の保全など住環境の再整備などが問題となっています。
千里丘陵開発の推進力となった千里ニュータウンと万博 千里山をはじめ吹田市の新たな交通系・道路系の整備は、既述の千里ニュータウンの完成や次項で述べる万国博覧会の開催が契機となりました。千里ニュータウン計画に伴い、基幹となる交通系として阪急千里山線の北への延長が予定されました。昭和38年(1963年)9月、千里山-新千里(現・南千里)間、約1.67kmの路線が開通し、同時に千里山線の名称が千里線に改められました。千里ニュータウンの造成に従い、昭和42年(1967年)4月、千里線が新千里から北千里まで延伸し、新千里駅は南千里と改称されました。
昭和40年(1965年)、千里丘陵での万国博覧会の開催が決定すると、梅田と新大阪駅を繋いで万博会場にも通じる路線の敷設が急務となりました大阪市営地下鉄一号線(御堂筋線)は吹田市域の江坂駅が終点です。それより北の千里中央駅までの路線は北大阪急行電鉄によって経営されることになりました。昭和45年(1970年)、大阪市営地下鉄一号線と北大阪急行電鉄が吹田市域に敷設され、万博期間中は万博中央口駅までの仮設路線が設けられました。
日本万国博覧会開催が道路・交通網整備を加速 昭和45年(1970年)、アジアで最初の万国博覧会として「人類の進歩と調和」をテーマに77カ国が参加し、北部の千里丘陵を会場に日本万国博覧会が開催されました。3月14日に開会式が行われ、3月15~9月13日までの会期中の入場者数6421万人は予想をはるかに上回るものでした。この日本万国博覧会の開催によって吹田の名が全国に知られるようになりました。当時日本は高度経済成長のピークであり、万国博覧会は東京オリンピックに次ぐ国家的プロジェクトでした。
万国博覧会開催を機に千里丘陵の開発はさらに進み、交通も新御堂筋、中央環状線、中国自動車道、吹田インターチェンジ、豊中岸部線(岸辺駅地下道)、市役所前の高架道路、北大阪急行などの道路、鉄道が一挙に整備されました。